マイクラ統合版で全プレイヤーの周りに不死のトーテムのパーティクル(緑のキラキラ)を連発するコマンドです。
動作確認動画
【マイクラ統合版コマンド備忘録】
— かきママ(かきうちかな) (@kakky_kakichan) March 16, 2025
execute as @a at @s at @e[type=zombie,r=6] run playsound random.anvil_land @s ~~~ 0.3 2 1https://t.co/14RxJKw1aN pic.twitter.com/FqHwNmFwn6
コピペ用コマンド
コマンドブロックの設定
- リピート
- 無条件
- 動力が必要
- 遅延 20
このコマンドの実行結果
サーバー上のすべてのプレイヤーの周囲6ブロック以内にゾンビがいる場合、そのプレイヤーは金床が落ちる音を聞き続けます。r=6の数字を変えると半径の範囲を変えられます。
音の大きさは通常の0.3倍(小さめ)で、ピッチは通常の2倍(高め)に設定しています。この音はプレイヤー自身にだけ聞こえ、他のプレイヤーには聞こえません。
この設定により、プレイヤーがゾンビの近くにいる限り、1秒ごとに警告音が鳴り続けることになります。動力が必要なので、レッドストーン信号が切れると音は止まります。
このコマンドのパーツごとの解説
execute
「実行する」という意味のコマンドです。他のコマンドをより複雑な条件や状況で実行するための基本コマンドです。
as @a
「as」は「~として」という意味で、すべてのプレイヤーの立場でコマンドを実行します。つまり、サーバー上の全プレイヤーそれぞれに対してこの処理が行われます。
at @s
「at」は「~の位置で」という意味で、@sは「self(自分自身)」を指します。つまり、各プレイヤー自身の位置を基準にします。この部分があることで、各プレイヤーの周囲6ブロック以内のゾンビを検出できます。
at @e[type=zombie,r=6]
二つ目の「at」は「~の位置で」という意味です。@eは「entity(エンティティ=生物やアイテムなど)」を指し、「type=zombie」でゾンビに限定し、「r=6」は各プレイヤーから半径6ブロック以内という条件を加えています。つまり、「プレイヤーから6ブロック以内にいるゾンビの位置で」という意味になります。
run
「実行する」という意味で、これ以降に記述するコマンドを実際に実行することを指示します。
playsound random.anvil_land
「音を鳴らす」というコマンドで、「random.anvil_land」は金床が地面に落ちる時の音を指定しています。この音は「カラーン」というような金属的な音です。
@s
この音を聞く対象を指定しています。ここでの@sは、最初のas @aで指定した各プレイヤーを指します。つまり、そのプレイヤーだけがこの音を聞くことができます。他のプレイヤーやゾンビなどには聞こえません。
~~~
音を鳴らす位置を指定しています。三つの~はそれぞれX、Y、Z座標を表し、すべて~だけなので、プレイヤー自身の現在位置を意味します。つまり、プレイヤーのすぐそばで音が鳴ります。
0.3 2 1
音の設定を指定しています。
- 「0.3」は音量(1が通常、小さいほど音が小さい)
- 「2」はピッチ(1が通常、大きいほど高い音)
- 「1」は最小音量(0〜1の間で、1だと距離による音量減衰なし)を表します
このコマンド全体をリピートコマンドブロックで実行すると、「レッドストーン信号が送られている間、すべてのプレイヤーの近くにゾンビがいると、そのプレイヤーに1秒ごとに金床の音を聞かせる」という効果になります。これはゾンビ警報システムとして使えるでしょう。夜間や洞窟探索時に、目に見えない場所からゾンビが近づいてきたことを音で知らせてくれます。
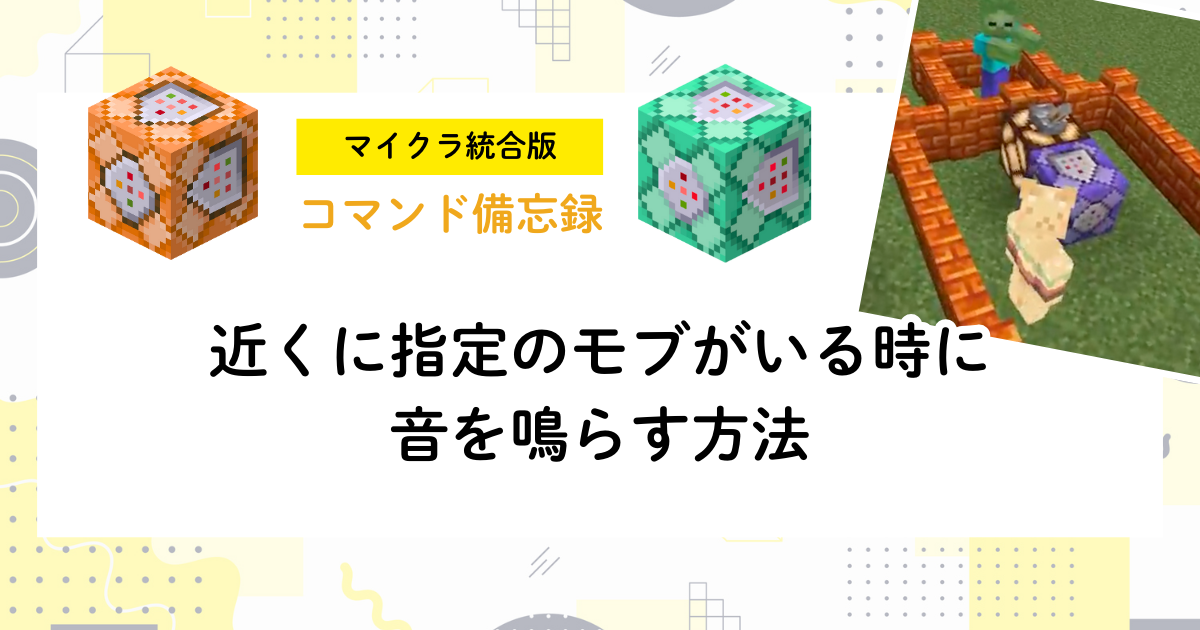
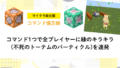

コメント